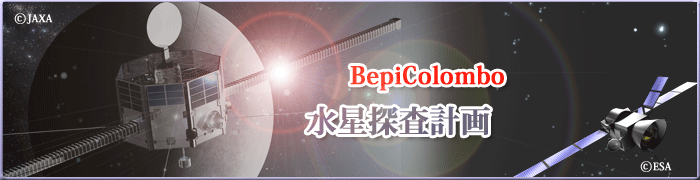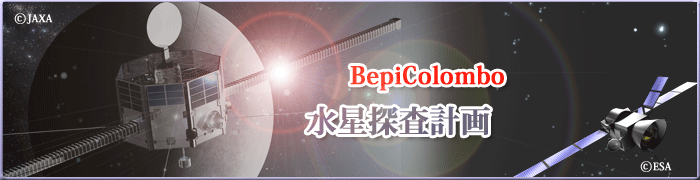|
|
水星への挑戦
~太陽系最内縁の未知の世界~ |
English>> |
|
|
|
|
|
|
水星:未知の世界 |
|
|
|
|
|
水星は、太陽系最内縁に位置する小さな地球型惑星(半径[2,440 km]は、月と火星の中間)である。
原始太陽系星雲の最も熱い領域で最後に生成された天体と考えられている。
水星は紀元前から知られているが、科学の進歩にも重要な役割を果たしてきた。
1631年に、Gassendiが水星の太陽面通過を発見した。
「惑星とは、太陽より圧倒的に小さいものだ!」という事実は、古典的な当時の概念を大きく揺さぶった。
1845年には、Le VerrierがNewton力学では説明できない水星近日点の移動を指摘した。
この解明は、Albert Einsteinが1915年に「一般相対論の証明」として見事に果たすこととなる。
ただ、現在に至っても、我々は水星そのものについてはわずかしか知らない。
太陽に近い水星は、地上の望遠鏡では観測困難である。
太陽から最も離れる時期(「秋の日出前」および「春の日没後」ですら、地平線の近くにいて大気に妨害される。
ハッブル宇宙望遠鏡も、太陽近傍の目標は故障を恐れて指向しにくい。
一方、探査機の訪問は強烈な熱や放射線によって阻まれ、
過去に米国のMariner10による3回の遭遇観測(1974-5)があるに留まる。
古代人も知っていた水星は今なお未知であり、太陽系の最重要探査対象の一つである。
日欧水星探査計画「ベピコロンボ(BepiColombo)」は、
この水星の磁場・磁気圏・内部・表層を初めて多角的・総合的に観測するものである。
主目的は、以下の二つである。
- 固有磁場を持つ地球型惑星は、地球と水星だけである。
水星の磁場・磁気圏の詳細な観測は、初めて地球を相対化することを可能とし、
「惑星の磁場・磁気圏」 の研究に大きな飛躍をもたらす。
(MMO探査機の主目標)
- 水星は「半径の3/4に達する巨大中心核」 (磁場があるのはこのせい?) など、特異な構造を持つ。
内部と表層の詳細探査によって、太陽に一番近い領域で起きた惑星形成の秘密に迫る。
(MPO探査機の主目標)
|
|
|
|
|
|
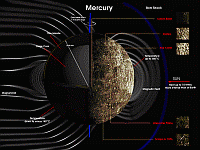
水星の内部・表層・磁場・磁気圏
[提供: BepiColombo-ESA homepage]
|
|
|
|
|
|
|
|
磁場:惑星内部の謎 |
|
|
|
|
|
これまで得られたわずかな情報は、水星の驚くべき特異性を示している。
水星は、ずば抜けて高い密度(5.43g/cm3)で知られる。
地球型惑星では、平均半径と密度との間に一定の関係が成り立つ(右図)が、
水星は高密度側に大きく外れる。
このことは、質量の約70%を占める巨大な中心核の存在と、他惑星とは大きく異なる元素組成を示す。
これは、水星の形成、すなわち太陽系初期の姿に起因すると考えられている。
|
|
|
|
|
|
|
「高密度」と関係する可能性があるのが、「磁場の存在」である。
同じ地球型惑星でも、金星には固有磁場が無い。
火星も、古い地殻に残る磁場の痕跡が最近発見されたものの、今はない。
「当たり前の存在」ではない磁場が、なぜ「より小さい水星にあるのか?」。
その理由は謎である。
磁場を作るには「溶けた中心核」が必要とされるが、小質量の水星で可能なのか?
磁場は惑星の内部に原因があり、また実際に近づかないと観測できない。
その解明には、水星の磁場・内部の詳細な情報と、地球との比較が必要である。
|
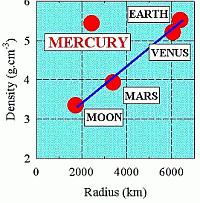
地球型惑星の半径と密度の関係
[Courtesy: BepiColombo Study Report]
|
|
|
|
|
|
|
磁気圏:地球と直接比較できる唯一の天体 |
|
|
|
|
|
水星は宇宙でも最小スケールの磁気圏を有する惑星として、
宇宙空間のプロセスを考える上で重要な存在である。
|
|
|
|
|
|
|
Mariner10は「磁気圏」を発見するとともに、
地球に相似した爆発的な高エネルギー電子流を観測した。
しかし、30年前の古い探査機の通過時データでは、
その詳細は未解明である。
「天体磁気圏」は、惑星・太陽・パルサー・銀河など様々なスケールで見られる。
最小スケールの水星磁気圏における「普遍性」の解明は、
地球・天体磁気圏の理解に重要である。
水星は十分な大気を有さず、磁気圏が直接地表と接続する。
地球の磁気圏では、大気(電離圏)が大きな役割を果たしている。
また太陽により近いため、太陽風の条件も地球と異なる。
これらの差は何をもたらすのか?
このような磁気圏がそもそも安定なのか、
またどのようなプロセスでエネルギーが蓄積・開放されるのかなど、
多くの議論があるが、定説はない。
水星のような異なる磁気圏の「独自性」の理解は、
その環境の役割の解明を通して地球・天体磁気圏の深い理解につながる。
|
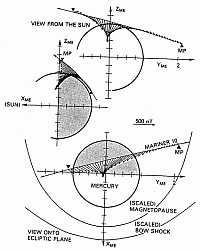
Mariner 10 第3回フライバイ
磁場・磁気圏の存在を確定
[Connerney and Ness, 1988]
|
|
|
|
|
|
|
大気:惑星表面からの便り |
|
|
|
|
|
水星特有の要素の一つとして、
地上望遠鏡によって近年発見されたNaを主成分とする希薄な「外圏大気」の存在がある。
この大気は、水星表面に太陽光・太陽風・磁気圏イオン・ダストなどが
衝突した結果、表面の物質がたたき出されてできていると考えられている。
|
|
|
|
|
|
|
「大気」は水星半径の数倍にまで広がり、
その量・分布は一日程度で大きく変動することが、明らかになってきた。
このような変動は磁気圏活動が大きな影響を与えているという説があるが、
詳しいことはわからない。
この大気の構造・組成・生成消失過程の解明には、
太陽風・磁気圏活動との同時かつ継続的な観測が必要である。
また、この組成の解明は、
水星の歴史の解明に重要な「希ガス」などの微量物質の検出につながる
ユニークな観測手段として有用である。
|
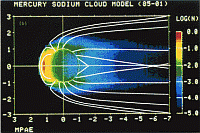
水星のNa大気・磁気圏(モデル)
[Ip, 1986]
|
|
|
|
|
|
|
表層・地殻:未知の構造 |
|
|
|
|
|
水星の表面は一見、月に似ている。
しかし、「高地と海の差があまりない」、「火山性平原があるのに火山跡が無い」、
「形成初期の冷却に伴って形成された?大規模地形」、
「直径1300kmに及ぶ巨大盆地と、その反対側表面に位置する奇妙な地形」など、謎が多い。
|
|
|
|
|
|
|
しかし、Mariner10で撮像した水星表面は約45%に留まり、また物質・化学組成は未知である。
また、地球からのレーダー観測は、「巨大火山跡」や「極域クレーター底の氷」など、
未確認だが重要な存在を示唆している。
水星全表面の地形・組成の詳細な情報によって、この惑星の初期形成過程の解明に
直接つながることが期待される。
|
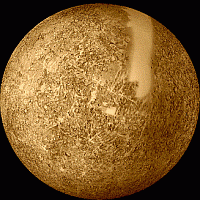
Mariner10が撮像した水星表面。
裏側は未撮像。
[Courtesy: NASA]
|
|
|
|
|
|
|
水星:資料室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|